![]()
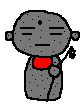 お四国病の部屋
お四国病の部屋
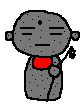
![]()
---------------------------------------------------------
最終更新日:2008/09/23 10:28
---------------------------------------------------------
![]()
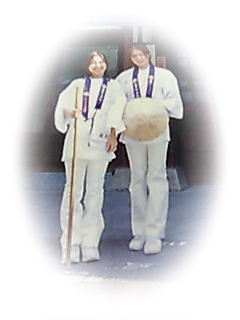
お遍路の出会いは、人だけではありません。
こんな素敵な名前の橋にも出会いました。
橋の下には清流が流れていました。
![]()
ひょいと 四国へ 晴れきってゐる (種田山頭火)
【お詫び】一部、礼所名と写真が食い違っているようです。申し訳ありません。
|
|
|
|
-------------------------------------------
ミニ八十八ケ所巡り(2005年10月10日 80番・国分寺で)
 四国八十八箇所お遍路の全記録
四国八十八箇所お遍路の全記録 
(お寺名をクリックすると、その巡礼記録へ飛びます。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() 【第1日目】 2005年3月14日(月)
晴 万歩計:32,797(歩行距離:約16km)
【第1日目】 2005年3月14日(月)
晴 万歩計:32,797(歩行距離:約16km)
大阪OCATから高速バスで、徳島へお国入り。(OCAT ⇒ 高速鳴門(¥3,150))
丸亀のチャットお友達のヒロさんに高速鳴門から車で霊山寺まで送って貰いました。
![]()
| 御詠歌 | 霊山の釈迦のみ前にめぐりきてよろずの罪も消え失せにけり |
 (10:00撮影)
(10:00撮影)
弘仁6年(815)、弘法大師は人間のもつ八十八の煩悩をなくそうと、この地を21日間修法している時に、数多くの菩薩が一老師を囲んで熱心に法を開いている光景を目の当たりにしたそうです。
釈迦如来がインドの霊鷲山(りょうじゅざん)で説法されていた様子にあまりにも似ていたことから、インド(天竺)の霊山を日本に移すという意味からこの名が付き、仏教五穀の法則に従って、四国を右回りに巡る遍路道を創って1200年余りになります。
------------------------------------------
これから始まるお遍路の旅に不安が一杯。
とにかく前に進もう!
ここで、不足していた菅笠・線香・ろうそくを買い足した。
![]()
| 御詠歌 | 極楽の弥陀の浄土へ行きたくば南無阿弥陀仏口ぐせにせよ |
(10:43撮影)
三方を山で囲まれた閑静な雰囲気の中に位置し、もともとこの地方は古くから開かれた土地です。
霊山寺と同様に行基が寺を開基し、弘法大師がこの地で21日間修業、その結願の日に現れた阿弥陀如来の姿を彫刻し本尊とし、八十八ヶ所の第二番札所に定めたそうです。
------------------------------------------
これでおいらも極楽へ行けそうな気がしました。無理、無理!
![]()
◆案内板◆
(11:25撮影)
こんな親切な看板や矢印のシールに助けられました。
道行く地元の方々とすれ違う時、手を合わされてちょっと恥ずかしい気がしました。
中学生たちもちゃんと、「おはようございます」と挨拶をしてくれました。
お昼は、地元の食堂で「煮物定食」(¥600)を頂きました。
食堂のおばちゃんに、「あんたは、色が白いねぇ。代わって欲しいわぁ。」と言われました。
この後、日焼けして、真っ赤(真っ黒)になったのですが。
![]()
| 御詠歌 | 極楽の宝の池を思えただ黄金の泉澄みたたえたる |
(13:24撮影)
聖武天皇勅願により天平年間(729~749)に建立されました。
当時は金光明寺と言われていましたが、後に弘法大師巡錫中に水不足で悩む地元の住民の声を聞き、大師が井戸を掘りました。
すると霊水が湧き出たため、その素晴らしさに感動した大師は堂宇を建てて金泉寺と改称したそうです。
------------------------------------------
まだまだ疲れは出ない。どんどん前へ進もう!!
(1時間毎に、靴を脱いで中を乾燥させました。なんでも、湿気があるとマメが出来るそうです。)
![]()
| 御詠歌 | 眺むれば月白妙の夜半なれやただ黒谷に墨染の袖 |
(13:52撮影)
開創年代ははっきりしませんが、弘法大師が長く滞在して修法し、一尺八寸の大日如来を彫って本尊にしたそうです。
この本尊の大日如来は八十八ヶ所中6ヶ所しかなく、真言宗では、「宇宙の中心、万物の根元とされる人々にあまねく、慈悲をもたらす最高の仏」とされます。
弘法大師は本尊にちなんで寺号を「大日寺」にし、第四番札所に定めたそうです。
その後歴史のうねりの中で、寺は何度も廃寺になってはその度に再建されています。
------------------------------------------
何がなんだか分からないが、般若心経もあげないでさっさと次のお寺へと急ぐ。
ありがたさは、今一感じられず。
まだまだ観光客(バスツアー客)が多い。
![]()
| 御詠歌 | 六道の能化の地蔵大菩薩導きたまえこの世後の世 |
(15:19撮影)
弘法大師が刻んだ本尊の勝軍地蔵菩薩は、高さ一寸八分(約5cm余り)で、甲冑(かっちゅう)を身につけ馬にまたがるという勇ましい姿をしています
その後、浄函上人が延命地蔵を彫り、その胎内に大師の菩薩を納めたと言われています。
------------------------------------------
まだこの辺りまでは、バスツアーの観光遍路さんが多い。
納経所で、添乗員さんが風呂敷に包んだ納経帳をどさっと出されて待たされると、さすがに不機嫌になりました。
こんなことで、いちいち腹を立ててはいけません!
(でも、私も俗界から来た一人。腹が立つのも無理はありませんよね。)
![]()
| 御詠歌 | 仮の世に知行争うむやくなり安楽国の守護をのぞめよ |
(15:55撮影)
この周辺には鉄サビ色の温泉が湧き万病に効くとされ、遠くから湯治に訪れる人も多かったそうです。
この地を訪れた弘法大師も、この土地から病疫から人々を救う薬師如来と深い因縁で結ばれていると直感されたそうです。
大師は坐像を刻み堂宇を建立して、八十八ヶ所第六番霊場と定めたそうです。
------------------------------------------
時間が早かったので、今夜の宿である「民宿・寿食堂」へ荷物を預けて、地蔵寺と安楽寺へお参りしました。
この寿食堂へは、あの民主党の管直人氏も泊まられたそうである。
民宿へ泊まるのは、人生で3度目かな。
名前が民宿と言うだけで、旅館とそれほど変わりはないですね。
(旅館業法での扱いが違うだけかも知れません。)
一時間毎に靴を脱いで、休憩したお陰か足にマメは出来なかった。やれやれ。
![]()
![]()
![]() 【第2日目】 2005年3月15日(火)
晴 万歩計:42,276(歩行距離:約21km)
【第2日目】 2005年3月15日(火)
晴 万歩計:42,276(歩行距離:約21km)
出発した時は寒かったが直ぐに温かくなった。
道行く小学生に挨拶された。
爽やかな朝だった。
![]()
| 御詠歌 | 人間の八苦を早く離れなば到らん方は九品十楽 |
(09:15撮影)
現在より3km余り奥の十楽谷に堂ヶ原という場所があります。
この地を訪れた弘法大師が阿弥陀如来を感得され、樟で本尊を刻み堂宇を建立して開基しました。
またその際、山号・寺名を命名するにあたり、生・老・病・死・愛別離苦(愛する者といずれ別れなければならない苦しみ)、求不得苦(求めるものが得られない苦しみ)など、人間が持つ八つの苦しみを阿弥陀如来の慈悲によって克服し、十の光明に輝く楽しみを得られるようにと願いを寺名に込めたと言われています。
------------------------------------------
清々しい朝のお参り。
今日も一日がんばって歩きます。
おかげさまで、まだ、足にマメは出来てません。
![]()
| 御詠歌 | たきぎとり水熊谷の寺に来て難行するも後の世のため |
(10:18撮影)
弘仁8年(817)、弘法大師が熊谷寺の閼伽ヶ谷(あかがたに)で修行している時に熊野権現が出現し、「長く衆生済度の礎とせよ」と告げ、一寸八分の金の観音像を授けたとそうです。
大師は等身大の千手観世音菩薩を刻み、その胎内に熊野権現から授かった観音像を納め、堂を建立して本尊として安置したのが、熊谷寺だそうです。
------------------------------------------
池のほとりから撮影したこの写真は、ナイスショット!
![]()
| 御詠歌 | 大乗のひほうもとがもひるがえし転法輪の縁とこそきけ |
(11:40撮影)
現在の場所から約3km離れた場所で弘法大師によって創建されました。
寺は壮大な伽藍を誇っていましたが、戦国時代にこの地を襲った長宗我部軍の兵乱激戦区にあたり、境内は兵火によってすべて焼失しました。
その後、土石流の影響もあり、正保年間(1644~1648)になって現在地に移され、「正覚山法輪寺(しょうかくざん ほうりんじ)」と名を改めて再興しました。
安政6年(1859)にまたしても失火により桜門だけを残して焼失してしまいます。
現在の本堂、大師堂などの堂塔は明治時代に再建されたものだそうです。
------------------------------------------
たんぼの中にあるお寺でした。
このお寺に入る前に、初めての「お接待」を受けました。
ビニールハウス栽培の「いちご」をご接待頂きました。
ありがとうございます。
でも、お札をお渡しして、「南無大師遍照金剛!」と3回、唱えるのをすっかり忘れちゃいました。
いちごをお接待してくださったおばあちゃん、ごめんなさいね。
![]()
| 御詠歌 | 欲心をただ一筋に切幡寺後の世までの障りとぞなる |
(11:40撮影)
弘仁6年(816)、弘法大師が旅僧姿で四国巡錫中にこの山麗に到った時、衣が相当痛んでいたそうです。
弘法大師が近くの民家に繕いの布を求めると、家の中で機を織っていた娘が、織りかけていた布を惜しげもなく断ち切って差し出してくれたそうです。
これに驚くと「ご用にたてていただくのは新しいものでなくては・・・」という答えがあったそうです。
この娘の好意に感動した大師は、「亡き父母のために観音像を彫って下されば・・・」という娘の願いを聞き、一夜で千手観音像を刻むと、娘を得度させ、更に秘密潅頂を授けたそうです。
すると娘の身から七色の光明が放たれ、たちまち千手観音の姿に変わったそうです。
これが仏法の即身成仏だそうです。
そこで弘法大師は嵯峨天皇に奉請して一寺を建立したのが、この切幡寺の始まりなのだそうです。
------------------------------------------
なかなか良い感じのお寺だった。
333段だったかの階段はきつかった。
でも、お寺の下の表装具屋さんが、荷物を預かってくださり、助かりました。
ありがとうございました。
(その表装具屋さんで、数珠かお守りか、なにかを買わないといけないかと思いましたが、何も買いませんでした。
また、帰りにはお茶まで接待して頂きました。)
![]()
清流・吉野川を渡る。
橋の上では、杖を突いてはいけない。
でも、ついつい突いてしまうのよね。
(大師さまが遍路の時、宿を断られて橋の下で寝たことから、橋では杖を突いてはいけないとのことです。)
![]()
| 御詠歌 | 色も香も無比中道の藤井寺真如の波のたたぬ日もなし |
(14:21撮影)
弘仁年間、この地に立ち寄られた弘法大師が、三面を山に囲まれた渓流の水清き仙鏡に心引かれたそうです。
現在の境内からさらに山中に入ったところにある八畳岩の上に護摩壇を築き、金剛不壊の道場として、17日間もの間、修行をしたといわれています。
そして境内に5色の藤をお植えになられたそうです。
その由来からこの寺は金剛山藤井寺の寺号となったのだそうです。
------------------------------------------
五月には藤の花が綺麗だとのことでした。
この日は、鴨島駅近くの「旅館さくら」(ガイドブックでは、「さくら旅館」)に宿泊。
旅館に行く途中で、鴨の湯に入った。
デッカイ風呂は気持ちがいい。
明日は最大の難所である「遍路ころがし」に挑戦。
体を休めるために、早めに就寝した。
![]()
![]()
![]() 【第3日目】 2005年3月16日(水)
晴 万歩計:35,879(歩行距離:約12km)
【第3日目】 2005年3月16日(水)
晴 万歩計:35,879(歩行距離:約12km)
朝は早めに出て、遍路転がしに挑戦。
お昼は、途中に店が無いので宿でお結びを作ってもらいました。
![]()
| 御詠歌 | 後の世を思えば恭敬焼山寺死出や三途の難所ありとも |
(14:20撮影)
標高938mの焼山寺山の八合目付近に位置するこの寺は八十八ヶ所中、一番の難所です。
弘法大師がこの地へ修行に訪れ、疲れから杉の木の下で眠って休んでいたところ、夢の中に阿弥陀さまが現れ、周囲の異変ぶりを告げられました。
目を覚ますと、山は火の海になっていました。
そこで大師が身を清め、真言を唱えながら山を上ると、火が徐々に消えていきました。
9合目あたりまで来た時、岩窟から大蛇が姿を現し、弘法大師の修行の邪魔をしようと更に向って来たそうです。
その時、光と共に虚空蔵菩薩様が現れ、その力を借りて大蛇を封じ込めたそうです。
その岩窟は、境内から歩いて30分の奥の院へ行く途中の道筋に残っています。
そして大師自ら三面大黒天を彫り、岩窟の上に安置して以来、天変地異が起こらなくなったそうです。
また、本尊の虚空蔵菩薩を刻み、焼け山の寺と名付け、梵語で水輪を意味する摩廬山と山号をお付けになられたそうです。
------------------------------------------
健脚5時間、並足で6時間、慣れない人で7時間の山道・遍路ころがしを歩きました。
ちなみに私は、6時間半ほどかかりました。荷物が重いこと、重いこと。
途中で諦めて帰ろうかと思いましたが、山の中から帰る術はなく、トボトボと歩きとおしました。
途中で、一緒になったお二人の方々と一緒に山道を励ましながら歩きました。
この方々と一緒でなければ挫けていたと思います。
このご一緒させて頂いたご婦人さんとは、結局、日和佐の23番まで一緒に歩かせて頂きました。
この日は、「なべいわ荘」へ宿泊。
ヒノキ風呂がよかったです。
宿には、人懐こい犬(雑種)がいました。
今まで禁酒していたのだが、さすがに疲れたのと無事に山を歩けたお祝いとして、ビールを一本頂きました。
この日以降、夕食にビールを一本頂くようになってしまいました。
![]()
![]()
![]() 【第4日目】 2005年3月17日(木)
曇り・少雨 万歩計:データ紛失(歩行距離:約23km)
【第4日目】 2005年3月17日(木)
曇り・少雨 万歩計:データ紛失(歩行距離:約23km)
昨日宿泊した「なべいわ荘」は、快適な宿だった。
みなさんに、お奨めの宿です。
![]()
| 御詠歌 | 阿波の国一の宮とはゆうだすきかけて頼めやこの世のちの世 |
(13:19撮影)
弘仁6年(815)、この地で修行中の弘法大師のもとに大日如来が現れ、「この地は霊地なり、心あらば一宇を建立せよ」と弘法大師に告げました。
そこで大日如来を刻み本尊として、堂宇を建てて安置したそうです。
------------------------------------------
昨日の山道が嘘のように感じられる下り道を歩いた。
静岡は三島のご夫妻と宿が一緒になり、昨日遍路ころがしで一緒に歩いたご婦人と私も入れて4人で歩いた。
道端には梅の花が咲いており、のどかな風景を楽しみました。
こんなところで生活できたら、幸せだろうなぁと思いました。
道端の農家の方から、ハッサクをお接待して頂きました。ありがとうございました。
途中、弱い雨に降られ、初めてポンチョを使いました。
大日寺には早く着き過ぎたので、名西旅館にて早風呂してゆっくり休憩をしました。
この名西旅館では、「柿の葉」から抽出した、筋肉痛用の塗り薬をお接待して貰いました。
![]()
![]()
![]() 【第5日目】 2005年3月18日(金)
(朝方少雨)晴 万歩計:41,754(歩行距離:約26km)
【第5日目】 2005年3月18日(金)
(朝方少雨)晴 万歩計:41,754(歩行距離:約26km)
朝7時に出立。
風が少し寒かった。
橋を渡ってどんどん歩いていると、地元の御婆さんに道が違うと呼び止められた。
あのまま真っ直ぐ歩いていたら、遠くへ行っていたことだろう。
![]()
| 御詠歌 | 常楽の岸にはいつか到らまし弘誓の船に乗り遅れずば |
(07:33撮影)
修行中に化身した弥勒(みろく)菩薩が多くの菩薩を従えて現れ、説法を行ったので、弘法大師は霊木にその姿を刻んで堂宇を建てて本尊にしたそうです。
この寺の境内には歩きにくい大岩盤で出来た「流水岩の庭園」が特徴となっています。
これはこの地に境内を移転する際に、山を切り崩し埋め立て、岩盤の奥に堂宇を建てたために、流水岩の庭が出来たようです。
------------------------------------------
この寺の庭のその荒々しい光景には感動しました。
年月を経ても人々の信仰は生きているのです。
![]()
| 御詠歌 | 薄く濃くわけわけ色を染めぬれば流転生死の秋の紅葉ば |
(07:51撮影)
天平13年(741)、聖武天皇が天下泰平を祈願して建立した全国66国分寺の一つだそうです。
------------------------------------------
駆け足でお寺を廻る。
![]()
| 御詠歌 | 忘れずも導きたまえ観音寺西方世界弥陀の浄土へ |
(08:21撮影)
このお寺は、天平13年(741)聖武天皇の勅願道場として創立されました。
その後、弘仁7年(816)に弘法大師がこの地を訪れ、等身大の千手観世音菩薩を刻んで本尊として、両脇侍に不動明王と毘沙門天を安置したそうです。
------------------------------------------
このお寺に着く前に、冷たい雨に降られた。
前の道は狭く、斜め横から撮影した。
![]()
| 御詠歌 | 面影を映してみれば井戸の水結べば胸の垢や落ちなん |
(09:17撮影)
弘仁6年(815)、この地を訪れた弘法大師は、この地域の水は濁っていて、村人たちが水不足に苦労していることを弘法大師が哀れみに思われたそうです。
そこで自らの杖で一夜のうちに井戸を掘られたところ、みるみる清水が湧き出しました。
その水に映った御自分の姿を石に彫られた御尊像は、日限大師(ひかぎりだいし)として祭られています。
------------------------------------------
さっきまでの雨が嘘のように快晴に。
さあ、これから徳島市内をぬけるぞぉ~!
俗界に足を踏み入れて、今までの修行が台無しにならないように、要注意です。
![]()
| 御詠歌 | 子を産めるその父母の恩山寺訪ふらひがたきことはあらじな |
(14:47撮影)
元々このお寺は、行基が厄除のために薬師如来を御本尊として刻み、大日山福生院密厳寺と号していたそうです。
そして、緒人の災厄を除く道場として、女人禁制の寺であったと言います。
100年余りを経たある時、修行中の弘法大師を母が訪ねてきたが会うことが許されなかったそうです。
そこで弘法大師は、ひと七日(一週間)滝に打たれ修行をし女人解禁の秘法を修め、母を寺内に招き入れ孝行を尽くしたそうです。
その事から、母養山恩山寺と寺号を改めたそうです。
------------------------------------------
徳島市内を通過。
俗界に久々に戻った感じがした。
夕方、冷たい風雨にさらされた。
これも修行の一つと思って前に進んだ。
徳島市内で一泊して、骨休みの予定だったが、頑張って先に進んだ。
(一泊していたら、きっと焼き鳥屋で一杯やっただろうな。)
![]()
![]()
![]() 【第6日目】 2005年3月19日(土)
晴 万歩計:35,881(歩行距離:約18km)
【第6日目】 2005年3月19日(土)
晴 万歩計:35,881(歩行距離:約18km)
天気はバッチリ。
だいぶ日焼けした。
(UVケアはしていない。)
昨日から土の道を歩かずアスファルトの道ばかりだ。
遍路にはやっぱり土の遍路道が好いなぁ。
![]()
| 御詠歌 | いつかさて西の住居のわが立江弘誓の母の乗りて到らん |
(08:10撮影)
聖武天皇の勅願により、天平19年(747)に行基が光明皇后の安産を祈願しつつ、念持仏として一寸八分(約6cm)の金の地蔵菩薩「延命地蔵尊」を掘り、それを本尊として堂塔を建立したのが始まりだそうです。
建立の時、飛んできた白鷺が橋の上にとまり、行基に建てるべき場所を暗示したそうです。
以来、この橋(現在の白鷺橋)に白鷺が止まっている時に橋を渡ると、仏罰を受けると言われています。
------------------------------------------
寺内でお婆さんに賽銭入れ袋の接待をしていただいた。
お婆さん、どうかお元気で長生きしてくださいね。
![]()
| 御詠歌 | しげりつる鶴の林をしるべにて大師ぞいます地蔵大釈 |
(13:43撮影)
八十八ヶ所で2番目に難所と言われ、急勺配な道をどんどん上がったところにお寺があります。
延暦17年(798)に垣武天皇の勅願により、開基されたのがこの寺の歴史に始まりだそうです。
この寺には不思議な伝説が残っています。
弘法大師がこの地で修行をされていると、霊雲のたなびく中、雌雄二羽の白鶴がかわるがわる翼をかざして金色の地蔵菩薩を守護しながら杉の梢に降りて来ました。
そこで弘法大師は、三尺の地蔵菩薩を彫刻し、その胸の部分に御降臨された一寸八分の金色に輝く地蔵菩薩を納めて御本尊とされたそうです。
------------------------------------------
荷物を宿の「民宿金子や」に置いて、お鶴さんへの山道を登った。
結構きつい山道であった。
宿への帰り道、お婆さんにお接待をしてもらった。
「これでジュースでも飲みなさい」といってお金を貰った。
お婆さんにとって、ジュース代と言えども大切なお金に違いなく、大変ありがたく思った。
「南無大師遍照金剛」(合掌)。
ところで、この日の宿は、部屋も晩御飯も最悪だった。
また、宿の女将さんも態度が横柄で最悪であった。
野宿した方がよかったかも知れないと思った。
(この近辺に、民宿はこの一軒しかないようだ。 こんなことを言っているようでは、まだまだ悟りは開けないな!)
![]()
![]()
![]() 【第7日目】 2005年3月20日(日)
晴 万歩計:33,222(歩行距離:約19km)
【第7日目】 2005年3月20日(日)
晴 万歩計:33,222(歩行距離:約19km)
鶴林江(かくりんじ)までは昨日打っていたので、宿からはタクシーで登ってそれから太龍寺へときつい道を歩いた。
タクシーは乗り合いで、お年寄りご夫婦が料金の大半(1420円のうち、1000円)を払ってくださった。
ありがとうございました。
![]()
| 御詠歌 | 太龍の常にすむぞやげに岩屋舎心聞持は守護のためなり |
(11:09撮影)
このお寺は、標高約600mの山頂付近にありますが、ロープウェイで楽に行け、山頂駅に着けば本堂へ続く長い石段と黒門が出迎えてくれます。
垣武天皇の勅願によって開かれたお寺で、弘法大師が自ら刻まれた虚空蔵菩薩が御本尊として本堂に安置されています。
幸福、人徳、財力、知恵を無限に授けてくれる仏様だそうです。
------------------------------------------
ここまでの山道は結構きつかった。(途中、水飲み場もない。)
昨日の宿で作ってもらったおにぎりは、梅干も入ってなく、たくあんも付いてなくて、2ケで200円もした。
それも焼きおにぎりで、食事のご飯の残りで握ったのではないかと思われた。
高いなあ~と思った。
(こんなことで文句を言っているようでは、まだまだ悟りが開けるのは、先のようだ。)
![]()
| 御詠歌 | 平等にへだてのなきと聞く時はあら頼もしき仏とぞ見る |
(15:15撮影)
弘法大師が延暦11年(792)、41歳の時にこの地に訪れ、母君が厄年にあたるため、一心不乱に厄除祈願をしていました。
すると、空中に五色の瑞雲がたなびき、その中にあらわれた梵字は薬師如来に姿を変え、光明が四方に輝きました。
そこで弘法大師が加持水を求めて杖で井戸を掘ると、乳白色の水が湧き出しました。
その霊水で身を清められた大師は100日間修行の後に薬師如来像を刻み、本尊として安置しました。
そして、この乳白色の水によって、人々が平等に救済されますように・・・と寺号を平等寺と定めたのだそうです。
------------------------------------------
このお寺の直ぐ横の「山茶花(さざんか)」でおやつにうどんを食べた。うまかった。
この日の宿は、少し離れた「清水旅館」(桑野駅前)にした。
平等寺まで車で迎えに来てくれた。
![]()
![]()
![]() 【第8日目】 2005年3月21日(月)
晴 万歩計:42,765(歩行距離:約21km)
【第8日目】 2005年3月21日(月)
晴 万歩計:42,765(歩行距離:約21km)
昨日の宿から平等寺まで車で送ってもらい、そこから海岸線を歩いた。
良い天気だった。
![]()
| 御詠歌 | 皆人の病みぬる年の薬王寺瑠璃の薬を与えまします |
(14:31撮影)
神亀3年(726)に行基が開基し、弘仁6年(815)に大師が平城天皇から、厄除け祈願寺を開くようにとの勅願を受けて本尊の薬師如来を刻んで安置し、厄除けの根本祈願寺としたそうです。
------------------------------------------
一国打ち完了!!
お遍路三日目から一緒に歩かせて頂いたご婦人と日和佐の食堂で軽く打ち上げをした。
なんと生ビールの旨いこと!
久々に熱燗も少々頂いた。
やっぱり俗界は好い。
夜は、独り焼き鳥屋で一杯やり、たばこも一本吸ってしまった。
(焼き鳥屋で隣り合わせたお客さんからの”お接待”タバコでした。)
あああ、せっかく禁煙していたのに勿体無いことをした。
(お遍路では、お接待を断ってはいけないことになっているから仕方なかった。)
日和佐の海岸には海亀が産卵に来るらしい。
とっても綺麗な海岸でした。
一国打ち完了の記念撮影。(一緒に歩いたご婦人に撮って貰いました。)
まあよく歩いたものだと関心してしまった。
![]()
![]()
![]() 【第9日目】 2005年3月22日(火)
晴
【第9日目】 2005年3月22日(火)
晴
日和佐から徳島まで列車で移動。
その後、高速バスで松山の叔父の家に遊びに行った。
![]()
![]() 【第10日目】 2005年3月23日(水)
雨時々曇り 車で移動
【第10日目】 2005年3月23日(水)
雨時々曇り 車で移動
叔父・叔母と一緒に、叔父の運転する車で松山市内を中心にお寺を廻った。
歩きはしなかった。
| 御詠歌 | いまの世は大悲のめぐみすごうさんついにはみだのちかいをぞまつ |
↓
(中略)
↓
| 御詠歌 | らいごうのみだのひかりの円明寺てりそふかげはよなよなの月 |
![]()
![]()
こうして無事、今回の遍路は終わりました。
長かったようで、短かったです。
皆様のご協力、叱咤激励に感謝します。
また、末筆ではありますが特に「安浦大師講」さまには、たいへん親切なご指導を頂き、ここに記してお礼を申し上げます。![]()
【四国88箇所の由来】
弘法大師が42歳のとき、四国八十八ヵ所の霊場を開いたとされている。また、弘法大師入定後、高弟真済がその遺跡を遍歴し始まったとされる説がある。八十八という数は、煩悩の数や、「米」の字を分解したもの、または男42、女33、子供13の厄年を合わせた数などという説がある。
4月1日、転勤で高松市へ移住。
これでまた思う存分、お遍路が楽しめます。
![]()
![]() 【お四国転勤編】
2005年4月29日(金)
晴 万歩計:41,993(歩行距離:約21km)
【お四国転勤編】
2005年4月29日(金)
晴 万歩計:41,993(歩行距離:約21km)
ゴールデンウィークが始まり、お四国は高松へ転勤して始めてのお遍路です。
JR四国の四国再発見切符を買って、朝4時58分高松駅初の普通電車に乗り、今治の先の大西駅に9時24分に着きました。
途中、電車のすれ違いで安浦大師講ご夫婦とお会いしました。
高知方面へお遍路に向かわれていました。
この日も快晴で、すっかり日焼けしてしまいました。
今治は全国有数の造船地区であり、また全国地番のタオルの生産地でもあります。
瀬戸内海の燧灘(ひうちなだ)に面し、とても穏やかな好い街です。
この日は、今治市に点在する6箇所の礼所を廻りました。
![]()
| 御詠歌 | くもりなきかがみのえんとながむればのこさずかげをうつすものかな |
(10:06撮影)
天平年間(729~748)、行基が不動明王を刻み、今治市の西北にある近見山の頂に七堂伽藍を建立したのが始まりだそうです。
平安時代に入り、弘法大師が嵯峨天皇の勅願を受け来錫し、荒れていた寺を再興されたそうです。
------------------------------------------
この山門は、今治城の城門の一つを譲り受けたものらしい。
サツキが綺麗だった。
![]()
| 御詠歌 | このところ三島に夢のさめぬればべつぐうとてもおなじすいじゃく |
(11:09撮影)
四国霊場で坊というのはここだけです。
かつて別宮大山積神社と隣接しており、明治初年までは大山祗神社の別当寺であったようです。
その縁起は今から1300年前にさかのぼります。
河野氏の始祖・越智玉興(たまおき)の弟である玉純は、文武天皇の勅願を受けて大三島の大山積明神に勧請し、法楽所として24坊を建立しました。
しかし海を渡らないと参拝にいけないため和銅5年(712)にその別宮を越智郡日吉村に移転したそうです。
同時に別当院寺として南光坊を含む8坊を移したそうです。
------------------------------------------
「寺」が付いてない珍しい礼所です。
納経所には、美人の方がおられ、ご朱印を頂いた。
オッサンの方へ進まなくて、よかった。
もう一度、訪ねてみたい気分になった。
これもお遍路の楽しみの一つかも知れない。
![]()
| 御詠歌 | みな人のまいりてやがて泰山寺来世の引導たのみおきつつ |
(12:10撮影)
この地を巡錫した弘法大師が、この村に伝え起こる悪霊の祟りからの毎年の川の氾濫を鎮める為、村民を指導して、堤防を建設、土砂加持の秘法を七座厳修されました。
その満願の日に、延命地蔵が現れ大師がその尊像を刻み一寺を建立したことからこの寺が始まったそうです。
------------------------------------------
写真は、カメラの紐が映ってしまい大失敗。
この後、コンビニのお弁当を蒼社川の川原で一人寂しく食べた。
![]()
| 御詠歌 | この世には弓矢を守る八幡なりらいせは人をすくうみだぶつ |
 (写真は、撮り忘れ。)
(写真は、撮り忘れ。)
木々に抱かれたような佇まいを見せる栄福寺は、開基は弘法大師で嵯峨天皇の勅願によって弘仁年間(810~824)に開かれたそうです。
大師がこの地を巡錫した際、周辺の海で海難事故が相次いでいる事を知り、海神供養の護摩供を厳修したそうです。
------------------------------------------
大師堂には千支の見事な彫刻がありました。
![]()
| 御詠歌 | たちよりてされいの堂にやすみつつ六字をとなえ経をよむべし |
(13:52撮影)
「おされさん」の愛称で親しまれる仙遊寺は、天智天皇の勅願により国守・越智守興公が堂宇を建立されました。
海抜約300mの山上にあるこのお寺の本尊は、千手観世音菩薩で、これには海から上がってきた竜女が彫り上げたそうです。
竜女は海から竜登川を伝って作礼山にやって来ましたが、一刀刻むごとに三度礼拝していたため、完成には幾日も要したそうです。
------------------------------------------
ここにたどり着く遍路道は、この日の中で一番きつかったです。
降りの山道はひざに来ます。
歳かなぁ?
![]()
| 御詠歌 | しゅごのためたててあがむる国分寺いよいよめぐむ薬師なりけり |
(16:06撮影)
風光明媚な唐子浜にほど近い、唐子山の麓にたたずむお寺です。
国分寺は、聖武天皇の勅願により、全国に建立されたお寺です。
伊予の国分寺は、天平13年(741)に行基が開基しました。
当時、七堂伽藍を備えた豪壮な大寺院だったようです。
弘法大師は、この地に長く留まり五大尊の絵像一幅を残しました。
堂宇は度々焼失と復興を繰り返しましたが、しばらくの間、茅葺きの小堂が寂しく建つのみだったそうです。
------------------------------------------
境内には、握手をして祈祷する修行大師の像もありました。
この日は、少し戻って「ホテル・コスモ・オサム」(朝食付¥5,000)に宿泊。
大きい風呂もあり、疲れが取れました。
![]()
![]()
![]() 【お四国転勤編】
2005年4月30日(土)
晴 万歩計:16,834(歩行距離:約5km)
【お四国転勤編】
2005年4月30日(土)
晴 万歩計:16,834(歩行距離:約5km)
この日は、伊予富田から電車に乗り伊予小松まで移動。
横峰寺は、一日で上り下りすると大変そうなので、次回の楽しみとしてパスしました。
![]()
| 御詠歌 | のちのよを思へばまいれ香園寺とめてとまらぬしらたきの水 |
(08:59撮影)
このお寺の歴史は古く、用明天皇(585~586)の病気平癒を祈願して聖徳太子が創建したそうです。
この時、金衣白髪のお老翁が飛来、本尊・大日如来を安置しました。
弘法大師がお寺の麓にさしかかった時、一人の女性が難産で苦しんでいました。
大師が栴檀の香を焚いて祈梼したところ、玉のような男児が誕生したそうです。
そこで大師は、唐から持ち帰った一寸八分の大日如来の金像を本尊の胸に納め、唐木栴檀の香を焚きながら、安産、子育て、お身代わり、女人成仏の四請願と秘法を寺に伝えて霊場に定められたそうです。
------------------------------------------
モダンな鉄筋コンクリート造の大聖堂。
聖徳太子の父・用明天皇が病気の平癒を願って建立したらしい。
天平年間には、行基も訪れたとそうです。
今まで、木道のお寺だったので、なんか奇異に感じられました。
![]()
| 御詠歌 | さみだれのあとにいでたる玉の井はしらつぼなるや一の宮かは |
(11:04撮影。撮り忘れて再度戻って撮影。)
大同年間(806~810)、弘法大師が来錫されました。
光明皇后を型どった十一面観世音菩薩を刻んで本尊とし、第六十二番札所と定めました。
当時は山手川・中山川の近くにあったため、幾度となく河川の氾濫に遭い、破損・再建を繰り返しました。
------------------------------------------
石柱には「一国一宮別当宝寿寺」と書かれている。
聖武天皇の時代に、勅令で伊予国一宮の法楽所(お経を上げるところ)として創建されたらしい。
三角の赤いコーンがなんとなく変でしたが、どけてまで写真は撮りませんでした。
![]()
| 御詠歌 | 身の中の悪しき悲報をうちすててみな吉祥をのぞみいのれよ |
(09:48撮影)
弘仁年間(810~823)、弘法大師がこの近くを通りかかったときに光を放っている檜を発見されました。
その木に一刀三礼して、毘沙聞天と脇仏の吉祥天、善尼師童子を刻み堂宇に安置したのが始まりとのことです。
------------------------------------------
ご本尊が昆抄門天というのは四国霊場の中では唯一ここだけらしい。
農家の信仰が厚い礼所とのことでした。
![]()
| 御詠歌 | 前は神うしろは仏ごくらくのよろづの罪をくだくいしづち |
 (写真は、撮り忘れ)
(写真は、撮り忘れ)
弘法大師は二度石鎚山を登り、ここで求聞持法を修めたそうです。
文徳天皇、高倉帝、後鳥羽帝、順徳帝、後醍醐帝など歴代天皇が厚く帰依したことでも知られています。
------------------------------------------
この礼所は真言宗石鉄派の総本山で、赤道色の山門を入ると桜並木の参道が続き、その脇には十三仏、薬師如来、不動明王などの像が並んでいました。
ここで偶然、松山の叔父夫婦・従妹に出会った。
なんでも従妹が休みで帰省し、叔父夫婦とドライブがてら、廻って来たそうであった。
びっくりした。
これも何かの縁かも知れないと、思いました。
この後、松山へ遊びに行き一泊して、高速バスで高松へ帰りました。
![]()
![]()
![]() 【お四国転勤編】
2005年5月5日(木)
晴 万歩計:34,391(歩行距離:約20km)
【お四国転勤編】
2005年5月5日(木)
晴 万歩計:34,391(歩行距離:約20km)
ゴールデンウィークのお休みの終盤、高松の近くへお遍路に出かけました。
朝、7時過ぎに出発。
近所のコンビニでおにぎりを買い、高松中央公園のベンチで朝食を済ませて、いざ屋島へ!
屋島は、番町から近くに見えるのですが、歩くと意外と遠いものでした。
![]()
| 御詠歌 | 梓弓屋島の宮に詣でつつ折りをかけて勇む武夫 |
琴電「かたもと」から遍路道へ。
今まで”赤色”だったシールが何故か”ぐんじょ色”だった。
なんで?
屋島山上にあって、源平合戦にも縁の深い寺だそうです。
753年に唐の鑑真が屋島にお堂を建てたのが始まりだそうです。
弘法大師が宝珠を投げ入れた「瑠璃宝池(血の池)」。
源平合戦の時、血で汚れた刀を洗ったら真っ赤に染まったので、「血の池」とも言うらしいです。
八栗方面を屋島より見る。
八栗寺は、まだまだ遠くに見えるなぁ~。
遍路道はキツイ!! 屋島ドライブ・ウェイは、歩行禁止。
段々の木を止めているのは「鉄筋棒」。
滑ってコケて、お尻の穴に刺さったら、絶対絶命!!
![]()
| 御詠歌 | 煩悩を胸の智火にて八栗をば修行者ならで誰か知るべき |
:唐へ行く前の弘法大師が、この山に登り八つの焼栗を埋めて旅の無事を祈願したそうです。帰国後、再び当地を訪れて求聞持法(ぐもんじほう)を修した時、天から五本の剣が降って来ると共に、山の鎮守である蔵王権現の御神託があったと言います。また八つの栗も無事に成長していたので、五剣山八栗寺と号した寺を建立したそうです。
高松市内に戻って遅い昼食。ビールも一本飲んじゃった!
![]()
![]()
![]() 【お四国転勤編】
2005年10月10日(月)
晴時々曇り・少雨 万歩計:52,000
【お四国転勤編】
2005年10月10日(月)
晴時々曇り・少雨 万歩計:52,000
体育の日、高松の五色台へお遍路に出かけました。
朝、9時過ぎに出発。
近所のコンビニでおにぎりを買い、JRに乗って国分寺駅へ!
帰りはずっと番長まで歩き、かなり遠く疲れました。
![]()
| 御詠歌 | 国を分け野山をしのぎ寺々にまいれる人を助けましませ |
天平13年(741)、聖武天皇の勅願により全国に建立された国分寺の一つです。
行基が十一面千手観世音菩薩像を安置して開基しました。
弘仁年間(810~823)には弘法大師がこの地に来錫し、本尊を修復、堂塔を増築したそうです。
当時は東西220m、南北240mの広大な寺域を持ち、金堂や鐘桜、七重塔、僧坊などが立ち並ぶ大院寺でした。
その後、天正年間(1579~1591)に兵火にかかり、本堂と鐘桜を残して伽藍を焼失、慶長年間(1596~1614)に讃岐国守・生駒一正(いこまかずまさ)によって再興され、江戸時代には高松藩主松平家代々によって庇護されました。
参道の両側には八十八ヶ所の本尊の石仏が並び、境内には、地蔵堂や社が点在しています。
また松並木も多く、見事な枝ぶりの緑に心がなごみます。
この道を上がって行くと、遍路転がしがある。(どっかで見た看板が道端にあった。)
久々の遍路転がし。でも、焼山寺への山道に比べたら、全然、へっちゃらだい!
![]()
| 御詠歌 | 霜さむく露白妙の寺のうち御名を称うる法の声ごえ |
五色台の一つ、白峯の山腹にある寺。
寺伝によると、弘仁6年(815)、弘法大師が白峯に宝珠を埋め閼伽井(あかい)を掘り堂を建立しました。
智証大師がこの山上に霊光を見、白髪の老翁に導かれて瀬戸内海を漂っていた霊木で千手観音を刻み、本尊としました。
老翁は当山鎮守の相模坊(さがんぼう)大権現だといわれています。
境内は、なかなか落ち着いていて雰囲気がとっても好かった。
山道はアスファルトじゃないので、きついけど脚には好いような気がする。
野に咲くコスモス。ああ、秋だねぇ。
根香寺への途中にある「足尾大明神」。
![]()
| 御詠歌 | 宵の間のたえふる霜の消えぬればあとこそ鐘の勤行の声 |
五色台の青峰山中にあり、深い緑に包まれた寺。
入唐前の弘法大師がこの地を訪れ、五つの峰に金剛界曼荼羅の五智如来を感得され、五大明王をまつり花蔵院(かぞういん)を建立しました。
後に天長9年(832)大師の甥の智証大師が当山を訪れ、山の鎮守である市ノ瀬明神の神託により、不思議な香を放つ霊木を刻んで千手観音像を刻み、これを本尊として千手院(せんじゅいん)を創建、この2院を総称して根香寺と号しました。
後の後白河上皇はこの本尊を深く信仰し、当寺を祈願所としたといいます。
天正13年(1582)の兵火により伽藍を焼失。高松藩主・生駒家と松平家の再建によるものです。
![]()
![]()
![]() 【お四国転勤編】
2005年10月29日(土)
晴 万歩計:29,508
【お四国転勤編】
2005年10月29日(土)
晴 万歩計:29,508
土曜日、昼から雨があがったので、高松市内の一宮寺へお出かけしました。
![]()
| 御詠歌 | さぬき一宮の御前に仰ぎきて神の心をだれかしらいう |
高松市郊外の田園地帯にある、こじんまりとした寺。
大宝年間(701~703)に義淵(ぎえん)僧正が開基し、当初は「大宝院(だいほういん)」と称した法相宗(ほっそうしゅう)の寺でした。
諸国に一宮が建立された時、行基によって堂塔を修築、讃岐国一宮・田村神社の第一別当職となり、寺号を一宮寺としました。
すぐそばにある「田村神社」。立派な神社で巫女さんも可愛かった。
![]()
![]()
![]() 【お四国転勤編】
2005年10月30日(日)
晴 万歩計:26,867
【お四国転勤編】
2005年10月30日(日)
晴 万歩計:26,867
四国再発見切符(¥5,500)を買って、早朝、高松駅4:58発の普通列車で伊予三島へお出かけしました。
この切符は、来年の1月29日まで有効です。
![]()
| 御詠歌 | おそろしや三つのかどにもいるならば心をまろく慈悲をねんぜよ |
標高450mの三角寺山の中腹に佇む伊予国最後の札所です。
天平年間(729~749)、聖武天皇の勅願により、弥勒菩薩の浄土を現して行基が開基しました。
弘仁6年(815)にこの地を来錫した弘法大師が本尊となる檜材一木造りの十一面観世音菩薩を堂宇に安置し、第六十五番札所に定めました。
伊予三島は、さすがに製紙工場の街。煙突の煙が気になりました。また、三角寺のすぐそばには、養鶏場かその糞の処理工場があるみたいで、プンプン臭ってました。(w
遍路の途中では、豚舎や養鶏場はよくあるみたいです。
![]()
![]() 【お四国転勤編】
2005年11月13日(日)
晴 万歩計:37,784
【お四国転勤編】
2005年11月13日(日)
晴 万歩計:37,784
あさから四国再発見切符で観音寺までお出かけしました。
![]()
| 御詠歌 | はるばると雲のほとりの寺に来て月日を今は麓にぞ見る |
観音寺からタクシーでロープウェイ駅まで約20分(2,700円)。日本一、高速のロープウェイで一気に山頂へ。(約7分)
標高927m香川県と徳島県の県境をまたぐ四国山脈に位置する雲辺寺は、霊場の中では最も高い場所にあります。「遍路泣かせ」と言われた、この急勾配な坂道は登りに2時間はかかる最大の難所とされてきました。今はロープーウェイで7分ほどです。霊山の趣に惹かれた当寺、16歳の弘法大師が延暦8年(789)に堂宇を建てたのが始まりです。以後は僧侶達の学問を修める場として栄えました。
「おたのみなす」には、腰掛けて願いを懸けるといいらしい。「彼女が出来ますように!」と。
67番大興寺への山道は整備されていて歩きやすい。落ち葉が脚に優しい。
雲辺寺と言うだけあって、雲が目線にある。最高!
![]()
| 御詠歌 | 植え置きし小松尾寺を眺むれば法の教えの風ぞ吹きぬる |
周りはのどかな田園風景が広がり、地元では「小松尾さん」と呼ばれ、親しまれている大興寺。寺の前の小さな橋を渡って仁王門をくぐります。この寺は、弘仁13年(822)、嵯峨天皇の勅願により弘法大師が熊野権現鎮護の札所として開いたのが始まりと伝えられています。
![]()
◆第68・69番礼所◆ 神恵院(じんねいん)・ 観音寺(かんおんじ)
| 御詠歌 | 笛の音も松吹く風も琴弾くも歌うも舞うも法のこえごえ |
| 御詠歌 | 観音の大悲の力強ければ重き罪をも引き上げてたべ |
2礼所とも近接。納経所も共通だった。もちろん300円×2=600円、料金を徴収されました。
![]()
![]() 【お四国転勤編】
2005年12月3日(土)
晴 万歩計:40,700
【お四国転勤編】
2005年12月3日(土)
晴 万歩計:40,700
あさから四国再発見切符で伊予小松までお出かけしました。
![]()
◆第60番礼所◆ 横峰寺(よこみねじ)
| 御詠歌 | たてよこにみねや山べに寺たててあまねく人をすくうものかな |
西日本最高峰・石鎚山系中腹にある札所は古くから遍路泣かせの難所と言われています。
開祖は修験僧の開祖・役行者小角(えんぎょうじゃおづぬ)。白雉2年(651)、星ガ森(石鎚山遥拝所)で修行中の役行者小角は、石鎚山頂で蔵王権現のお姿を見て、そのままの姿を石楠花(しゃくなげ)の木に刻んで小堂に安置しました。
弘法大師が42歳の厄除け開運祈願の修行の為、この山へ登り星祭りの修行を行い、その結願の日に役行者と同じ権現様の姿を見せました。そこで大師はこの山を霊山と定め大日如来を刻み本尊として安置し第六十番札所に定められたといいます。
本堂は神社風の権現造りで、どっしりとした美しさを漂わせる建物の風情は圧巻です。また境内は石楠花の名所としても名高いです。
:横峰寺への遍路道。林の中を通り抜けて、山を登りました。
:横峰寺山門。伊予小松駅から登ったので、この山門は、お参りの後から通りました。
:本堂。バスでのお遍路さん達がお参りされ変えられた後でしたので、ひっそりと静かな好い雰囲気でした。
:大師堂。本堂と正対しています。
:境内内には人数が少なく静かでした。
![]()
![]() 【お四国転勤編】
2005年12月18日(日)
晴時々雪 万歩計:36,144
【お四国転勤編】
2005年12月18日(日)
晴時々雪 万歩計:36,144
朝から四国再発見切符でJR本山(香川県)までお出かけしました。日本列島には大寒波が押し寄せており、とっても寒かったです。
◆第70番礼所◆ 本山寺(もとやまじ)
| 御詠歌 | 本山に誰が植えける花なれや春こそ手折れ手向けにぞなる |
:田園風景の中に、遠くからでも見える五重塔は、この札所を目指すお遍路さんにとって格好の目印です。本山寺は大同2年(807)、平城天皇の勅願により弘法大師が一夜ほどで建てた「一夜建立」の寺であると伝えられています。
◆第71番礼所◆ 弥谷寺(いやだにじ)
| 御詠歌 | 悪人と行き連れなんも弥谷寺ただかりそめも善き友ぞよき |
:「仏の山」として昔から民間信仰を集めている弥谷山。札所に続く石段の脇には、死者の霊魂を弔うためか五輪塔が多く置かれ、樹木の陰には古い墓が並んでいます。また急勾配な石段は262段+108段あり、八十八ヶ所でも有数の難所であるといわれています。
:大池のほとりにある遍路休憩所。吹きさらしで寒かったけど、屋根がありありがたい休憩所だ。四国はこうした遍路さんへの心遣いの国でもある。
◆第72番礼所◆ 曼荼羅寺(まんだらじ)
| 御詠歌 | わずかにも曼荼羅おがむ人はただふたたびみたびかえらざらまし |
:曼荼羅が創建されたのは、推古天皇4年(596)で、弘法大師の先祖である佐伯家の氏寺として建立されたものです。当時は世坂寺(よさかじ)と称していたが、大同2年(807)、唐から帰国した弘法大師は亡き母の菩薩を弔うため、青龍寺を模して伽藍を建て、大日如来を刻んで本尊としました。
◆第73番礼所◆ 出釈迦寺(しゅっしゃかじ)
| 御詠歌 | 迷いぬる六道衆生救わんと尊き山にいずる釈迦寺 |
:曼荼羅寺を出て更に車道を登っていくと出釈迦寺が見えてきます。この山はかつて、倭斬濃山(わしのやま)と呼ばれていました。弘法大師は7歳で仏道に入って救世の大誓願を立てようと倭斬濃山の山頂に立ち、「仏門に入って多くの人々を救いたい、この願いが叶うならば釈迦如来よ、現れたまえ。もし、願いが叶わぬならば、一命を捨ててこの身を諸仏に捧げる。」と願をかけ、断崖絶壁に身を投げました。しかし、落下していく大師の体の下方に紫雲がたなびき、蓮華の花に座した釈迦如来と羽衣をたなびかせた天女が現れました。雲上で大師を抱きとめ「一生成仏」の旨を告げました。このお告げにたいそう感激した大師は、後に釈迦如来を刻み本尊として堂宇を建てたのがこの寺の始まりだそう。この時に倭斬濃山も我拝師山に改めたと言われています。その頂上には奥の院が作られ、捨身ヶ嶽禅定(しゃしんがたけぜんじょう)と呼ばれています。
◆第74番礼所◆ 甲山寺(こうやまじ)
| 御詠歌 | 十二神味方に持てる戦には己れと心かぶと山かな |
:この辺りは、弘法大師の故郷で、幼少の頃は泥の仏像や草木の小堂を作って遊んだといわれる地です。平安時代初期、弘法大師が善通寺と曼荼羅寺の間に寺院を建立しようと霊地を探していました。すると、甲山の麓で一人の翁に出会い、「私は昔からこの地に住み、人々に限りない幸福と利益を与え、仏の教えを広めてきた聖者である。この地に寺を建立すると良い。そうすれば、その寺は私がいつまでも守護するであろう」と告げたといいます。大師はさっそく石を割って、毘沙門天像を刻み、山の岩窟に安置しました。これが甲山寺の始まりです。
◆第75番礼所◆ 善通寺(ぜんつうじ)
| 御詠歌 | われすまば よもきえはてじ 善通寺 ふかきちかいの のりのともしび |
:ここは弘法大師誕生の地で真言宗善通寺派の総本山にして高野山、東寺とともに大師三大霊場の一つに数えられています。広大な境内は、伽藍と呼ばれる東院と誕生院と呼ばれる西院に分かれ、併せて45万平方メートルにも及びます。
◆第76番礼所◆ 金倉寺(ごんぞうじ)
| 御詠歌 | まことにも神仏僧をひらくれば真言加持の不思議なりけり |
:智証大師は弘法大師の姪を母に持つ、天台寺門宗の開祖です。弘仁5年(814)に生まれ、幼少の頃から教典を読んでいました。霊感も強く、今でいう大霊能者だったようです。5歳の頃、大師の前に訶梨帝母尊(かりていもそん)が現れたと伝えられています。
![]()
![]() 【お四国転勤編】
2005年12月25日(日)
晴
【お四国転勤編】
2005年12月25日(日)
晴
朝から四国再発見切符で今年最後のお遍路にお出かけしました。とっても寒かったです。
◆第77番礼所◆ 道隆寺(どうりゅうじ)
| 御詠歌 | 願いをば仏道隆に入りはてて菩提の月を見まくほしさに |
 :寺伝えによると、開基は和銅5年(712)。領主の和気道隆が薬師如来を刻み堂宇を建立したことで、その後、唐より帰国の弘法大師に道隆の子朝祐が師事、大師自らが道隆の薬師像を胎内仏とした薬師如来を刻み本尊としました。その後は大師の弟・法光大師、甥・智証大師など名僧が代々の住職を務め、伽藍も造営されたが、兵火により壊滅し江戸時代、歴代住職の尽力により本堂、大師堂、鐘桜、妙見宮などの伽藍、300mほど離れた畑の中に本坊と護摩堂があり、かつての寺域の広大さをしのばせている。
:寺伝えによると、開基は和銅5年(712)。領主の和気道隆が薬師如来を刻み堂宇を建立したことで、その後、唐より帰国の弘法大師に道隆の子朝祐が師事、大師自らが道隆の薬師像を胎内仏とした薬師如来を刻み本尊としました。その後は大師の弟・法光大師、甥・智証大師など名僧が代々の住職を務め、伽藍も造営されたが、兵火により壊滅し江戸時代、歴代住職の尽力により本堂、大師堂、鐘桜、妙見宮などの伽藍、300mほど離れた畑の中に本坊と護摩堂があり、かつての寺域の広大さをしのばせている。
◆第78番礼所◆ 郷照寺(ごうしょうじ)
| 御詠歌 | 踊りはね念仏申す道場寺拍子そろへて鉦を打つなり |
 :青ノ山の麓の高台にあり、「厄除けうたづ大師」として信仰を集めている郷照寺は神亀2年(725)に行基により開基。弘仁6年(815)にはこの地を弘法大師が訪れ自作の尊像を刻み厄除けの誓願をなされました。当時は真言宗で「道場寺」と称していましたので、御詠歌には「道場寺」の名が残っています。この寺は一遍上人の関係により、中興され、室町時代には守護大名の庇護も得て栄えたが、長宗我部軍の兵火により伽藍を焼失しました。寛文4年(1664)、高松藩主・松平頼重により再興されました。
:青ノ山の麓の高台にあり、「厄除けうたづ大師」として信仰を集めている郷照寺は神亀2年(725)に行基により開基。弘仁6年(815)にはこの地を弘法大師が訪れ自作の尊像を刻み厄除けの誓願をなされました。当時は真言宗で「道場寺」と称していましたので、御詠歌には「道場寺」の名が残っています。この寺は一遍上人の関係により、中興され、室町時代には守護大名の庇護も得て栄えたが、長宗我部軍の兵火により伽藍を焼失しました。寛文4年(1664)、高松藩主・松平頼重により再興されました。
◆第79番礼所◆ 天皇寺(てんのうじ)
| 御詠歌 | 十楽の浮き世の中をたずぬべし天皇さえもさすらいぞある |
 :寺伝えによると、弘仁年間(810~823)、弘法大師がこの地にある金山の岩窟で修行中霊験を感じ、その近くにある八十場の泉を流れていた霊木で十一面観世音菩薩、阿弥陀如来、愛染明王を刻みました。当時は「妙成就寺摩尼珠院(みょうじょうじゅじまにじゅいん)」と号していました。保元元年(1156)、保元の乱に敗れた崇徳(すとく)上皇は讃岐へ配流。現在の坂出市内にあった雲井御所(くもいごしょ)、木丸殿(このまるでん)で過ごしたが、当院へもよく来られました。長寛2年(1164)8月、この地で上皇崩御。都から葬儀の指示があるまでの20日間、遺体を八十場の泉に浸けて保存され、棺は当院に安置されました。
:寺伝えによると、弘仁年間(810~823)、弘法大師がこの地にある金山の岩窟で修行中霊験を感じ、その近くにある八十場の泉を流れていた霊木で十一面観世音菩薩、阿弥陀如来、愛染明王を刻みました。当時は「妙成就寺摩尼珠院(みょうじょうじゅじまにじゅいん)」と号していました。保元元年(1156)、保元の乱に敗れた崇徳(すとく)上皇は讃岐へ配流。現在の坂出市内にあった雲井御所(くもいごしょ)、木丸殿(このまるでん)で過ごしたが、当院へもよく来られました。長寛2年(1164)8月、この地で上皇崩御。都から葬儀の指示があるまでの20日間、遺体を八十場の泉に浸けて保存され、棺は当院に安置されました。
![]() 【お四国転勤編】
2006年1月3日(火) 晴
【お四国転勤編】
2006年1月3日(火) 晴
今年初めてのお遍路にお出かけしました。寒かったです。
◆第86番礼所◆ 志度寺(しどじ)
| 御詠歌 | いざさらば今宵はここに志度の寺祈りの声を耳にふれつつ |
推古天皇33年(625)、薗子という尼が霊木で本尊を彫り、お堂を建てたのが寺の始まりです。その後、天武天皇10年(681)、藤原不比等が妻である海女の墓を建立して「死度道場」と名付けました。その息子の房前(ふささき)が持統天皇7年(693)行基とともに堂宇を拡張し、僧侶の学問所や信者の修行の場となりました。縁起にも語られる「海女の玉取り伝説」は、謡曲「海士(あま)」のもとになっています。歴史のある寺には寺宝も多く、菅原道真筆「仁王経二巻」が納められています。堂々とした仁王門は、本堂とともに讃岐藩主・松平頼重が寄進したもので、日本でも有数の名門とたたえられる。
◆第87番礼所◆ 長尾寺(ながおじ)
| 御詠歌 | あしびきの山鳥の尾の長尾寺秋の夜すがらみ名をとなえよ |
天平11年(739)、行基が道ばたの柳の木で聖観音像を彫り安置したのが始まりといわれています。大同年間(806~810)、弘法大師が入唐にあたり訪れて、年頭七夜の護摩祈祷を行いました。帰国後再び来錫した大師は入唐の大願成就を感謝し、大日経一字一石の供養塔を建立したといいます。
このページのご感想を遍路の回覧板、または、アンケートのページからお寄せ下さい。
(C)MNN(Mizui's News Network)All Rights Reserved.Since1996